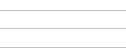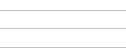|
メガネはアイデア産業 〜小売りから仕掛けるメガネ革命〜
2. メガネ工場で働いた少年時代
吉田は昭和12年、中小の町工場がひしめく東大阪で、4人兄弟の次男として生まれた。父親の鶴吉はメガネの下請け工場を経営する実直な職人。気に入らないことがあると、豪快にお膳をひっくり返してしまうような昔気質のところがあった。吉田は、その父親に従い、小学校3年生から工場の仕事を手伝った。学校から帰ると、工場の職人たちに混じってメガネのネジ穴にネジを入れて締め、いつも辺りが暗くなるまで100ダース、1200本のネジ入れをするのが日課だった。
「3時頃、家に帰ったら決まって工場の方から『タケヒコ〜』と父の呼ぶ声がするんですわ。単純作業やから、毎日やっていれば小学生でも熟練してくる。こんなの機械でやればいいのに、といつも思っていました」。
仕事嫌いの吉田少年は、当時、机の代わりに使っていたミカン箱の前に座り、勉強をするフリをしてよく仕事をサボった。すると、父親に「この子は将来、ノラ(仕事をしないでブラブラする人)になりよるぞ」と言って叱られた。
そんな吉田も学校では野球が上手な少年として、周囲の人気者だった。しかし、中学生になると、工場の仕事が忙しくなり、好きな野球もできなくなった。決して裕福とは言えない生活の中で、吉田は父親の背中を見ながらメガネづくりのイロハを学んだのだった。
母親のチヨとの思い出も厳しい生活を映し出すようなものが多い。
戦後の混乱の中で母親は小さい吉田を連れて和歌山まで魚を買いに出かけ、大阪で行商をしていた。小学生の時には、吉田を連れだってメガネの集金に幾度も出かけている。
 |
| 幼年期の吉田(左端) |
ある冬の寒い日、職人の給料が払えないため、母親と吉田少年は未払い金がたまっている業者のもとを訪れた。道中、母親が吉田少年につぶやく。
「タケヒコ、情けないな。どうせ、行ってもお金くれへんのにな」。
集金先に着くと、案の定、業者は支払いを渋った。母親が粘り強く交渉して食い下がると、業者はついに札束を投げ渡し、1万円札がバラバラと床に落ちた。
「お金を放ったらあきませんがな」。
母親はそう言いながら、腰をかがめて1枚1枚、1万円札を拾い集めるのだった。
「もう二度と売りにきたるか!」。
冬の夜道を歩きながら、悔しがる母親の言葉が吉田の耳に悲しく響いた。 |