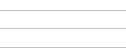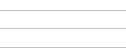| 企業は永続と見つけたり 〜情報処理産業の水先案内人〜
5. 損をしない経営
北大阪計算センターはすぐに従業員100人の会社に成長したが、誕生したばかりであるだけに、会社の体質は脆弱で管理者の不足という問題を抱えていた。そんな中、昭和46年にニクソンショックが経済界を直撃する。一気に不況色が強まる中、下請業である情報処理産業への影響も深刻で、北大阪計算センターの受注量は激減した。西川氏は合理化策としてパンチャーを半分に削減してこの難局を乗り切ろうとしたが、建て直しは難しく、期末決算で赤字を計上。北大阪計算センターは創業3年目にして会社存亡の危機に立たされたのだった。
昭和47年、西川氏は森のもとを訪れた。
そして、会社の置かれている状況を説明すると、こう切り出した。
「いま会社に必要なのは実務家の管理能力で、私の力ではもうどうにもならない。ついては、代表権を持って経営に当たって欲しい。それがダメなら、私は店はたたもうと思っている」。
森は西川氏の申し出を真摯に受け止めた。もともと自分が青写真を描いた事業だけに思い入れもあった。そして経営参加を決意すると、光洋精工に辞表を提出。37歳の若さで北大阪計算センターの代表取締役専務に就任する。
森は即座に経営の建て直しに着手すると、光洋精工時代の人脈を使って大手企業などエンドユーザー直結型の仕事を増やし、不安定だった受注構造を解消。従業員もスリム化し、パンチャーの仕事が毎日9時半から5時までびっしりと埋まるようにスケジューリングして、作業効率を上げた。
そして、「独立独歩の精神を持て」という年頭方針を掲げて役員から従業員まで全ての人の発奮を促す一方、「お客様に仕事をさせていただいている」というモットーを作って社員の意識改革を促したのだった。
その結果、北大阪計算センターの売上げは前年比30%増と回復。前年の赤字も一掃して見事に息を吹き返した。
翌年、森はさらに「信用」「採算」「融和」という社是を制定して企業理念をはっきりと打ち出し、全社員の意識をひとつに束ねたのだった。
 |
こうして森と西川氏の共同経営がスタートしたが、当初、2人の周囲では「全く異質の2人はそのうち仲たがいするに違いない」という見方が大勢を占めていた。
ところが、そんな周囲のうがった見方は同社が順調に売上げを伸ばしていく中で、覆されていく。社長であり、大株主でもある西川氏と、会社再建を任された森は最初から「資本」と「経営」を分離する理想の形で会社運営を行うことができたため、それが思わぬ効果となって会社の成長を導いたのだった。
森もこう述懐する。
「初めから絶対に赤字を出せない環境で経営を任されたことは、あとあと会社を運営していくうえで非常にプラスになった。その『損をしない経営』が成功につながるひとつの要因だった」。
会社の再建が軌道に乗ると、森はさらにパンチャーの教育にも力を入れた。それまでパンチャーの確保は、大手企業が社内で養成した人材を新聞広告などの宣伝方法で引き抜くのが主流だった。しかし、やがて業界内でパンチャーの引き抜き合戦が繰り広げられるようになると、人件費が次第に上昇。また、大手企業がパンチ入力をこぞって外注委託し始めたため、パンチャー不足が顕著となったのだ。この流れを見て、森はすばやく社内にパンチャーの教育課を新設。未経験者を採用して、パンチ技術に加え会社方針やマナー研修なども行った。さらにパンチャーが育ってくると、森はこれまでの受託業務に加え、パンチャーの出向・派遣事業に乗り出したほか、システム部門を設けてソフト分野へも進出。経営の多角化を図っていった。
そして、北大阪計算センターは順調に規模を拡大し、創業から10年目の昭和53年には売上高6億円、従業員数200人の会社に成長。その急成長をけん引した森は、業界で「パンチの神様」と呼ばれるようになり、情報処理サービス業界の草分けとしてその名が知れ渡るようになる。
森は毎年恒例となった年頭方針で、全従業員を前に高らかにこう述べた。
「8年前に7人の従業員で始めた当社は、もはや我々だけの会社ではなくなった。これからは社会的責任のある会社になったことを十分自覚し、お客様に仕事をさせていただいているという気持ちで仕事に励んで欲しい」。 |