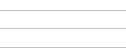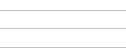| “おもてなし”が夢を生む ~タクシー業に賭ける親子100年の挑戦~
第一部 多田清(相互タクシー株式会社 創業者)
6. 「選ばれるタクシー」を目指して
大正時代から始まったと言われる日本のタクシー産業は戦前、戦中の揺籃期を経て、戦後になると、大きな発展を見せる。昭和 23 年には道路運送法が施行され、三輪オートバイを改造した半タクやアメリカ軍専用の外車ハイヤーまで、焼け跡に立つバラック建てのタクシー会社が雨後のタケノコのように出現。無免許の白タク営業も全盛期を迎え、タクシー運転手たちは乗客を取り合い、 24 時間中、無制限に街を走り回った。この頃、タクシーの中には少しでも多くの乗客を乗せるため、全速力で目的地に向かう乱暴な運転も横行し、国内外から戦時中の“神風特攻隊”をもじって「神風タクシー」と揶揄され、社会問題となることもあった。
 |
| 紺の詰襟と制帽を着用する乗務員 |
そんな時代、清は大阪市内の復興に歩調を合わせるように、営業所システムの整備を進める。営業所システムとは、街を走行しながら乗客を乗せる「流し営業」とは対照的に、営業所に待機して、チケットを持ったお客様の連絡を待って配車する営業方法のことである。この政策を進めるには、清がすでに手を打っていた「戦後のインフレ対策」が存分に効力を発揮した。つまり、営業所を整備する土地対策と企業にチケットを購入してもらうための産業界の株式保有を、すでに大方済ませていたからである。清は、株式所有という形で多くの企業に投資する一方、それらの企業にチケットを購入してもらうという絶妙の経営センスを見せた。
営業所を開設するに当たっては、十代の頃に菓子屋の失敗で痛感した「商売は地の利」という教訓が生かされる。清は、運転手の毎日の日報を管理者に詳しく点検させ、距離数や乗客の動きをこまめにチェックすることで、「どこに、どのようなお客様がいて、どこまで行かれたか」を洗い出した。そうすることで、集客地点を正確に把握し、大阪、京都で計 40 ヶ所の拠点を次々に設けていった。
また、清はのりば戦略を進めると同時に、「すべては、お客様のため」という考え方を、さらに徹底した。この頃になると、乗務員は全員が紺の詰襟に白のワイシャツ、青ネクタイを着用し、他社が自動ドアを導入している時代に、乗務員によるドアサービスを徹底した。
こうした利用者の乗り心地に対する清の徹底したこだわりは、数々のエピソードとして後世に多く伝わっている。
その一つが、「身長170㌢㍍以下、太った者はダメ」という、かつてあった運転者雇用基準。これは、車を降りてドアを開閉する乗務員が、お客様を見下ろしたり、威圧感を与えないようにという配慮である。
相互タクシー社長を務める小野幸親氏も、こんなエピソードを聞いたことがある。
「お客様の乗り心地にこだわる先代は、シートのシーツカバーにもこだわっていました。シーツカバーはコットンの白で、いつもノリをきかして、3日ごとに洗濯する。生地も目が細かすぎず、荒すぎず、皺になりにくいものを選び、生地番まで指定していたようです。昭和初期の段階から、安心して乗っていただくのはもちろん、清潔で気持ちよく快適に乗車できるタクシーを目指していたのが先代でした」。
清は、「雲助タクシー」と揶揄された時代にも、常に“選ばれるタクシー”を目指していた。 |